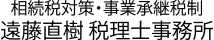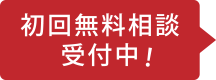相続税の申告期限までに遺産分割ができない場合
コラム
2025年8月11日 月曜日
1 相続税の申告期限はいつ
相続税の申告期限は被相続人がお亡くなりになったことを知った日から10か月です。
一般的には実際にお亡くなりになった日から10か月以内で申告が必要になります。
2 相続税の申告までの流れ
相続税の申告を行う場合の一般的な順序は次のとおりとなります。
2-1 必要書類の準備
①お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本
②法定相続人全ての戸籍謄本
③お亡くなりになった方が不動産を所有されていた場合は、不動産の名寄帳又は固定資産評価証明書
④預貯金や有価証券などの残高証明書
⑤生命保険金などの支払明細書
⑥葬式費用や支払債務の領収書
⑦相続人全員の印鑑証明書
⑧相続人全員のマイナンバーが確認できる書類
2-2
総則財産を国税庁が定める「財産評価基本通達」を基に相続財産の評価を行う。
2-3
相続人間で「誰がどの財産相続する」のかを協議し、遺産分割協議書を作成する。
2-4
上記内容を基に申告書を作成し、被相続人の住所を管轄する税務署へ申告書の提出を行う。
2-5
法定申告期限(相続開始から10か月)までに一括して納付を行う。
3 申告期限までに遺産分割が終了しない場合はどうなるのか
相続税の申告期限は原則、相続開始を知った日か10か月となっています。
仮に10か月以内に遺産分割が終了しなかったとしても、申告期限が延長になることはありません。
では申告期限までに遺産分割が終了しなければどのように申告書を作成するかをご説明していきます。
3-1 民法上の相続分
相続税の申告期限までに遺産分割協議が終了しなかった場合は、民法上の相続分で申告することになります。
民法上の相続分とは下記のとおりとなります。
①配偶者と子供が相続人である場合
配偶者2分の1 子供(2人以上の時は全員で)2分の1
②配偶者と親が相続人である場合
配偶者3分の2 親(2人以上の時は全員で)3分の1
③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上の時は全員で)4分の1
4 具体的な計算
では具体的にどのように未分割財産の計算を行い相続税の申告書を作成していくか説明したいと思います
4-1(例題1)
次の例の場合、各相続人の相続税申告書に記載する課税価格はいくらになるでしょうか。
①被相続人甲の相続人は、配偶者乙、子A、子Bの3名です。
②被相続人の遺産は100,000,000円です。
③債務及び葬式費用はなかったものとします。
4-1-1 各相続人の課税価格は以下のとおりです。
配偶者 50,000,000円
子A及び子B 25,000,000円
4-2(例題2)
次の例の場合、各相続人の相続税申告書に記載する課税価格はいくらになるでしょうか。
①被相続人甲の続人は、配偶者乙、子A、子Bの3名です。
②被相続人の遺産は100,000,000円と死亡保険金20,000,000円(受取人は配偶者乙)です。
③債務及び葬式費用はなかったものとします。
4-2-1 各相続人の課税価格は以下のとおりです。
配偶者 55,000,000円
子A及び子B 25,000,000円
配偶者乙が取得した死亡保険金はみなし相続財産となり、被相続人甲の固有の財産とは認められず遺産分割の対象にはなりません。
また、死亡保険金には相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。
今回の事例では法定相続人は配偶者乙及び子A、Bの3名であるため、非課税枠は500万円×3人=1,500万円となります。
死亡保険金の金額は20,000,000円であることから
20,000,000-15,000,000=5,000,000円が課税価格に計上されることになります。
4-3(例題3)
次の例の場合、各相続人の相続税申告書に記載する課税価格はいくらになるでしょうか。
①被相続人甲の続人は、配偶者乙、子A、子Bの3名です。
②被相続人の遺産は100,000,000円と死亡保険金20,000,000円(受取人は配偶者乙)です。
③子A及び子Bは生前に以下のとおり被相続人から贈与が行われていた。
子A:10,000,000円(相続時価格 10,000,000円)
子B:10,000,000円(相続時価格 5,000,000円)
④債務及び葬式費用はなかったものとします。
4-3-1 各相続人の課税価格は以下のとおりです。
配偶者 62,500,000円
子A 18,750,000円
子B 23,750,000円
この例題の遺産分割の基となる金額は次のとおりとなります。
100,000,000円(相続開始時の財産)+10,000,000円(子Aに対する特別受益)+5,000,000円(子Bに対する特別受益)=115,000,000円
配偶者の法定相続分は115,000,000×2分の1=57,500,000円となります。
57,500,000+5,000,000(みなし相続の課税対象部分)=62,500,000円
子Aの法定相続分は115,000,000×4分の1=28,750,000円
28,750,000-10,000,000(特別受益)=18,750,000円
子Bの法定相続分は115,000,000×4分の1=28,750,000円
28,750,000-5,000,000円(特別受益)=23,750,000円
5 相続税の申告期限までに遺産分割が終了しない場合のデメリット
申告期限までに遺産分割が終了しない場合は以下の特例が適用できません。
5-1 配偶者の税額軽減の特例
相続税の申告において配偶者が取得した財産については、法定相続分又は1億6000万円までは税額軽減の対象となり、結果的に税金がかからないケースがほとんどです。
しかし申告期限までに遺産分割が終了しない場合はその特例を使うことができません。
ただし、申告時に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出することにより法定申告期限から3年以内に遺産分割が終了すればこの特例を適用することができます。
5-2 小規模宅地の特例
相続や遺贈によって取得した財産のうち、相続開始の直前において被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用の使用されていた宅地等のうち一定のものがある場合は、相続税の課税価格に算入される価格が減額されるというのもです。
減額割合は以下のとおりです。
①特定居住用宅地 330㎡まで 80%減額
②特定事業用宅地 400㎡まで 80%減額
③貸付事業用宅地 200㎡まで 50%減額
こちらの特例に関しても、配偶者の税額軽減の特例同様に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出することにより法定申告期限から3年以内に遺産分割が終了すればこの特例を適用することができます。
5-3 修正申告及び更正の請求
遺産分割が終了せずにやむを得ず未分割の状態で申告書の提出を行った場合、相続税の申告処理はまだ終わったわけではありません。
最終的に遺産分割が終了すると、未分割の状態の課税価格に増減が生じます。
課税価格が増えた場合はそれに伴って修正申告書の提出が必要となり、最終的な納付金額を納める必要があります。
また、減少した人も「更正の請求」という処理を税務署に対して行い、納めすぎとなっている税金を還付してもらう必要が生じます。
いずれの処理にしても大変手間のかかるものです。
6 相続争いをさけるには
相続財産の大小にかかわらず相続争いは発生します。
被相続人の生前に話し合いをしていたとしても避けられない場合もあります。
しかし、納付資金の確保や財産の具体的な評価額を把握していれば、ある程度は遺産分割がスムーズに進むのではないかと考えます。
生前の相続対策により納付資金を確保し無用な争いごとを避けるためにも当事務所に一度ご相談いただけたらと思います。
カテゴリー: コラム