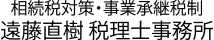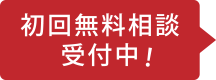相続時精算課税と相続税の節税について④
コラム
2025年7月12日 土曜日
相続時精算課税と相続税の節税との関係をについて、最終的な私なりの考えをお伝えしたいと思います。
〔前回までのおさらい〕
相続税の節税方法とは
【相続財産の総額を減らす】
《相続財産の総額を減らす方法》
・親族などに生前贈与を行う
・預貯金を死亡保険金に置き換えることで「相続税における死亡保険金の非課税枠(500万×法定相続人の数)」を適用する
・不動産を購入することにより、評価額を圧縮させ相続財産の総額を減少させる
【各贈与税の課税の特徴と相続税の関係】
《相続時精算課税》
・相続時精算課税に基礎控除の110万円が創設された
・この110万円以内の贈与については相続時に加算の対象とはならない
・この110万円以内の贈与については初年度に「相続時精算課税の届け出」を提出しておけば毎年の申告は不要
・基礎控除のほかに特別控除が2,500万円ある
・基礎控除110万円を超える贈与については、全て相続発生時に贈与時の価額で加算される
《暦年贈与》
・基礎控除は110万円である
・基礎控除以下の贈与の場合、申告手続きは不要
・令和7年1月1日以降の贈与の場合、相続財産への加算期間が7年に延長
【資産運用について】
日本は世界に比べて資産運用(株式投資など)に対して消極的である。
資産運用をせずに普通預金に預けておくことは「日本円」に投資をしていることと同じことである。(普通預金の金利0.2%)
預金をしておくだけではインフレ(物価高)に追いつけず、結果的に財産は目減りしていく。
《資産運用シミュレーション》
相続時精算課税の特別控除額が2,500万円あるので、投資金額を一括払い2,500万円とする。
また、運用期間については、60歳から相続時精算課税が適用できるため60歳から85歳までの25年間とする。
〔資産運用後の価額(税引き前)〕
約8,400万円(運用利益5,900万円)
さてここからは最終章です。
相続時精算課税と相続税の関係について私なりの結論を申し上げます。
〔何のために相続税の節税を行うのか〕
原点に立ち戻っての質問です。
税金を納めたくないだけであるなら、資産を持たないようにすればいいだけです。
しかし実際はそういうことではありません。
答えは「一生懸命に作り上げた資産を次の世代に少しでも多く残したい。」ではないでしょうか。
これからの時代は少子化が進み、社会保険の負担の増加、加えて物価高により生活が苦しくなってくるといわれています。
少しでも多くの資産を次の世代に残し、生活が楽になってほしいと考えることは、ごく自然なことだと思います。
そのためには少し考え方を変える必要があると思います。
【結論】
私が考える相続時精算課税と相続税の節税との関係については次のとおりです。
・60歳になったら相続時精算課税を適用し、できるだけ早く2,500万円を贈与する
・同時に相続時精算課税の基礎控除である110万円以内の贈与を毎年行う
・受贈者(子や孫)は贈与でもらった金額を資産運用に充てる
つまり、早めに次の世代に資産を移転させ、もらった側は資産運用により資産を増やしていくということです。
《財産を減少させるだけでなく、もらった側が財産を増やす》
相続時精算課税の特別控除である2,500万円を利用した場合、その金額は相続時に加算されることになりますが、もらった側が資産運用を行えば、運用益だけで相続税を十分賄える可能性があります。
上記の資産運用シミュレーションの結果はできすぎと思われるかもしれません。
しかし、資産運用はリスクを伴うものであり、現時点で資産運用を行っていない方も実は「日本円」に投資していることになり、現在インフレという物価高に悩まされています。
なお、投資信託の場合、市場に長く資産を置いておくほど「元本割れのリスク」が低くなります。
また市場に置いている期間が長いほど「複利効果」の恩恵を受けやすくもなります。
《時間を有効に使う》
当たり前ですが、時間は皆さんに平等に与えられたものです。
特に資産運用の場合、運用期間が長ければ長いほど運用効果も大きいと言われています。
先に説明した「複利効果」や「元本割れのリスク」は代表的なものです。
ただし、今後の世界情勢や税制改正など不透明な部分があることも確かです。
だからと言って何もしないことは、「何もしないことのリスク」とも言えます。
《今からでも間に合うのか》
間に合うこともあります。
資産運用の場合、短期間の運用では長期に比べてどうしてもリスクが高くなってしまいます。
しかし以下の方法は今からでも十分間に合います。
・死亡保険金の非課税枠の活用
仮に法定相続人が2人の場合、生命保険の非課税枠は500万円×2人」=1,000万円です。
相続税の税率が20%だった場合、200万円の節税になります。
・不動産の購入
3,000万円の預金で3,000万円の不動産(居宅)を購入した場合、不動産の評価額は約2,100万円となり、相続税の税率が20%だった場合、180万円の節税になります。
本当に必要な不動産であれば、十分検討する余地があると思います。
(個人的には投資用の不動産の購入には反対です。)
・相続時精算課税の活用
相続時精算課税の基礎控除110万円を利用した贈与の場合、相続開始直前の贈与だったとしても相続財産への加算はありません。
仮に2年間で110万円×2人×2年間=440万円の贈与が行われたとして、相続税の税率が20%だった場合、88万円の節税になります。
大きな節税にはなりませんが、何もしないよりはよっぽどましです。
・暦年課税贈与の活用
生前贈与の相続財産への加算の対象者は「相続又は遺贈により財産を取得した者」であるため、これに該当しない方(孫や、相続人の配偶者、相続する予定のない相続人など)に対する贈与は有効です。
なお、相続税の税率は最低10%です。
仮に18歳以上の子や孫に500万円贈与した場合の贈与税は485,000円(実効税率9.7%)となります。
500万円に対して10%の相続税50万円を納めるか約49万円の贈与税を納めるかということになります。
この場合ほとんど納税額は変わりませんが、相続税の税率が20%の場合は100万円の相続税を納めるか約49万円の贈与税を納めるかの違いがでてきます。(前回の回答です。)
贈与税と相続税の税率の差を利用するということです。
次の世代になるべく多くの資産を残す方法の一つに生前贈与や相続税の節税の節税があります。
大事なのは、現状を把握し少しでも早く行動に移すことだと思います。
カテゴリー: コラム