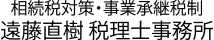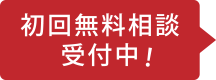令和7年分路線価公開
コラム
2025年7月2日 水曜日
令和7年7月10日、令和7年分の路線価が国税庁より発表されました。
【香川県】
香川県の平均変動率は0.1%の下落でした。
33年連続の下落であり、下げ幅は2024年より0.2ポイント小さくなっているということです。
県内で最も路線価が高い丸亀町商店街は1平方メートルあたり38万円で、2024年から2.7%上昇しました。
高松駅・サンポート地区での大型施設の建設や高松中央商店街の再開発などの影響で人の流れが増加しているためと思われます。
県の中心部は価格が上がり、郊外は下がっている印象です。
余談ですが・・・
当事務所付近の路線価は1平方メートルあたり55,000円となっています。
先日事務所付近に所在する分譲地の広告がポストに投函されており、その分譲地の1坪当たりの分譲価格は約39万円でした。
路線価は1平方メートルあたりの価格であるため、1坪に換算する場合約3.3倍する必要があります。
55,000円×3.3=181,500円(1坪あたりの路線価)
路線価は地価変動の安全を考慮しており、時価の8割程度と言われています。
つまり時価相当に換算すると
181,500円÷0.8=226,875円になります。
時価換算しても実際の分譲価格とだいぶ差がありますね。
路線価の価格 1坪=約18万円
実際の分譲価格 1坪=約39万円
不動産の購入が相続税の節税に使われる所以です。
【全国】
なお全国平均の変動率は2.7%の上昇となっております。
変動率の上昇は4年連続であり、平成22年から現在の方法で集計を始めて以降、最大の伸び率であるとのこと。
なお、四国4県の変動率は0.3%の下落で、全国12エリアの中で唯一の下落でした。
《路線価とは何か》
ここで路線価についての復習です。
相続税や贈与税を計算する場合の土地の価格については「時価」で評価することとなっています。
しかし、一般の方が相続税などの土地の時価を把握することは簡単ではありません。
そこで、相続税等の申告の便宜や課税の公平を図る観点から、国税局では毎年、土地の評価額の基準となる路線価と評価倍率を定めて公開しています。
ここでよく勘違いされている例を挙げると、路線価公開前(6月30日以前)に死亡した人の相続税を計算する際に使用する路線価は、旧の路線価ではないということです。
例えば
令和6年1月1日に死亡・・・・・令和6年分路線価
令和7年1月1日に死亡・・・・・令和7年分路線価
ということです。
死亡した年の路線価を使用することとなるため、令和7年1月に死亡した人が不動産を所有していた場合は、令和7年分の路線価が公開されるまで実質申告することができないということになります。(鑑定価格で申告する場合を除く)。
【不動産の評価方法】
不動産の評価方法についてのおさらいです。
相続や贈与が発生した場合における不動産の評価は何を見たらいいのか?
お客様からよく質問を受ける内容です。
「路線価を確認しても路線価が記載されていない」「農地はどのように評価するのか」など実際に評価しようとしても分からないことがたくさんあります。
そこで、具体的な手順を確認したいと思います。
1 財産評価基準書の確認
財産評価基準書とは路線価や評価倍率表のことです。
毎年7月に国税庁から発表されるもので路線価は財産評価基準書に含まれます。
まずは路線価を確認する前に評価倍率表で、路線価により評価する物件か又は評価倍率表により評価する物件かを確認します。
評価する物件の地域や地目によって評価方法が異なりますので注意が必要です。
2 評価倍率表に「路線」と記載がある地域は路線価により評価を行う地域なので路線価を確認します。
農地の場合「市比準」「周比準」と記載されている地域は宅地並みに評価する必要があるため「路線価」を使用する場合があります。
3 宅地「1.1」や田「30」などと記載されている地域は市町村が発行する固定資産税評価額にその倍率を掛けて評価します。
評価する地目や地域によって評価方法がことなりますので、まずは評価倍率表でどの評価方法を使用するのかを確認することが非常に重要です。
また、評価倍率表には「〇〇道路沿い」や「都市計画法上の用途地域の定められている地域」など細かく区分が分かれているため市町村で確認を要する場合もあります。
要約すると
宅地・・・路線価又は評価倍率
農地・・・評価倍率又は路線価等で宅地並みに評価をしたものから造成費相当額を控除
(農地を宅地並みに評価する場合、付近に路線価等が付されていない場合は市役所等で近傍宅地を確認する必要があります)
ということになります。
※雑種地等はさらに複雑になりますので今回は省略します。
簡単に説明しましたが実際評価しようとすると地域によってはかなり複雑になりますね。
次に路線価とそれ以外の評価についてのおさらいです。
ここで国・県から発表されている公示地価・基準地価との位置付けを確認したいと思います。
【公示地価・基準地価・路線価】の位置付けについて
・公示地価・・・調査主体は国(国土交通省)である。毎年1月1日時点の価格を発表している。土地取引を行う際の標準的な価格として捉えられている。
・基準地価・・・調査主体は都道府県である。毎年7月1日時点の価格を発表している。公示価格との最も大きな差は評価時点が1月1日か7月1日かである。公示価格の補完的な位置づけとして捉えられている。
・路線価・・・・調査主体は国税庁である。毎年1月1日時点の価格を発表している。主に相続税や贈与税の評価を行う際に利用される。路線価には市町村が使用する「固定資産税路線価」というものもあり、評価の安全性を考慮して、通常の「路線価」は公示地価の8割程度、「固定資産税路線価」7割程度となっている。
カテゴリー: コラム