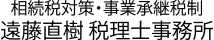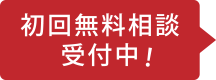「特定居住用小規模宅地」の特例について
コラム
2025年4月19日 土曜日
今回は相続税申告の大きな節税要素の一つである「特定居住用小規模宅地」の特例について解説していきたいと思います。
「小規模宅地の特例」の概要につきましては以前に解説しておりますので巻末の記事をご確認ください。
《特定居住用小規模宅地とは》
特定居住用小規模宅地とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等で、被相続人の配偶者又は一定の要件を満たす被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。
★チェックポイント
【誰が居住していた家の敷地が対象?】
特定居住用小規模宅地の対象となる土地は被相続人が居住していた建物の敷地はもちろん、被相続人と生計が一である被相続人の親族が居住していた建物の敷地も特例の対象となります。
なお、相続開始の直前において被相続人が老人ホーム等に入所したことにより居住の用に供していなかった場合には、一定の条件のもと、被相続人の居住の用に供していたとみなされます。
※一定の条件
・被相続人が要介護認定又は障害支援認定を受けていたこと
・被相続人が対象となる施設に入所していたこと(養護老人ホーム、有料老人ホームなど)
【誰が相続しても特例の対象となるのか?】
特定居住用小規模宅地の特例は誰が相続しても適用できるというわけではありません。
誰が居住していた物件を特例の適用対象にするのかによって要件が変わってきます。
〔被相続人が居住していた物件の場合〕
・配偶者が取得
特例適用対象になります。
・同居の親族が取得
相続税の申告期限までその物件を所有し、かつ、居住している場合は適用可能です。
・別居の親族が取得
いわゆる「家なき子特例」と言われているものです。
要件として
1 被相続人に配偶者がいないこと
2 被相続人が居住して以下家屋に居住していた被相続人の相続人がいないこと(一般的には独居状態のことを指します。)
3 取得する相続人が、相続開始前3年以内に持ち家を持っていないこと(相続人の配偶者、親族、関係法人が所有していてもだめ)
4 取得する相続人が現在居住している家屋の所有権を、いずれの時においても所有したことがないこと
5 その相続した物件を相続税の申告期限まで所有していること
〔被相続人と生計を一にしていた親族が居住していた物件の場合〕
・配偶者が取得
特例適用対象になります。
・被相続人と生計を一にしていた親族が取得
特例適用対象になります。
・別居の親族が取得
特例適用の対象にはなりません。
【建物の所有者は誰でもかまわないのか?】
〔被相続人が居住していた物件の場合〕
建物所有者は被相続人か被相続人の親族に限られます。
なお、建物所有者が被相続人の親族だった場合は、土地・建物の貸借について使用貸借(地代・家賃なし)でなければいけません。
〔被相続人と生計を一にしていた親族が居住していた物件の場合〕
この場合も同様に地代・家賃の授受があった場合、特例適用はありません。
(まとめ)
「特定居住用小規模宅地」の特例は適用が可能であれば大幅に相続税を減額できる制度です。
ただし、過去に無理やりこの特例を適用しようといろいろ知恵を絞って相続税の減額を行ってきた結果、要件としてはかなり複雑なものになってきました。
特に「家なき子特例」に関しましては、税制改正を繰り返した結果要件を認識するのも一苦労となっています。
相続税と不動産との関係は切っても切れないものとなっています。
不動産の購入・売却・居住用・事業用といろいろなパターンが存在しますが、将来のことを見据えた賢い選択を心掛けたいものですね。
参考:【小規模宅地の概要】
《小規模宅地の特例とは》
個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等のうち、一定のものがある場合には、一定の面積の部分については、評価を減額することができるという制度です。
簡単に言うと、お亡くなりになった方や生計を一にしていた親族が、亡くなる直前に住んでいた家屋の敷地や、事業に使用していた建物・構築物の敷地について通常評価した金額より一定金額を減額することができるということです。
つまり評価が減額できるということは、納める相続税が少なくなるということです。
《小規模宅地の種類》
では「小規模宅地の特例」にはどのような種類があるかというと、以下の3種類になります。
〇居住用の小規模宅地
〇事業用の小規模宅地(貸付事業を除く)
〇貸付事業用の小規模宅地
大きく分けると以上の3種類に分かれます。
特徴としては、どの小規模宅地に該当するかによって、特例に該当する限度面積・減額割合が変わってきます。
ちなみに各限度面積・減額割合は以下のとおりです。
〇居住用の小規模宅地 限度面積330㎡ 減額割合80%
〇事業用の小規模宅地(貸付事業を除く)限度面積400㎡ 減額割合80%
〇貸付事業用の小規模宅地 限度面積200㎡ 減額割合50%
例えば、「居住用の小規模宅地」を例にすると、自宅の敷地が面積330㎡、評価額2,000万円だった場合、
2,000万円×330㎡/330㎡×80%=1,600万円(小規模宅地による減額)
2,000万円-1,600万円=400万円(相続税評価額)
となり、1,600万円の評価減となります。
相続税の税率が仮に20%だった場合、320万円の相続税が減額されたことになります。
非常に大きな減額ですね。
このように「小規模宅地の特例」は要件さえ満たせば非常に有効な節税になるわけです。
カテゴリー: コラム