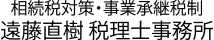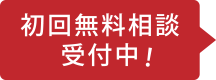小規模宅地の特例(貸付事業用宅地編)
コラム
2025年3月30日 日曜日
今まで何度か取り上げてきました「小規模宅地の特例」について、今回はその中の一つ「貸付事業用小規模宅地」について解説していきたいと思います。
《小規模宅地の特例とは》
まずはおさらいとして「小規模宅地の特例」の概要について説明したいと思います。
個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等のうち、一定のものがある場合には、一定の面積の部分については、評価を減額することができるという制度です。
簡単に言うと、お亡くなりになった方や生計を一にしていた親族が、亡くなる直前に住んでいた家屋の敷地や、事業に使用していた建物・構築物の敷地について通常評価した金額より一定金額を減額することができるということです。
つまり評価が減額できるということは、納める相続税が少なくなるということです。
《小規模宅地の種類》
では「小規模宅地の特例」にはどのような種類があるかというと、以下の3種類になります。
〇居住用の小規模宅地
〇事業用の小規模宅地(貸付事業を除く)
〇貸付事業用の小規模宅地
大きく分けると以上の3種類に分かれます。
特徴としては、どの小規模宅地に該当するかによって、特例に該当する限度面積・減額割合が変わってきます。
ちなみに各限度面積・減額割合は以下のとおりです。
〇居住用の小規模宅地 限度面積330㎡ 減額割合80%
〇事業用の小規模宅地(貸付事業を除く)限度面積400㎡ 減額割合80%
〇貸付事業用の小規模宅地 限度面積200㎡ 減額割合50%
例えば、「居住用の小規模宅地」を例にすると、自宅の敷地が面積330㎡、評価額2,000万円だった場合、
2,000万円×330㎡/330㎡×80%=1,600万円(小規模宅地による減額)
2,000万円-1,600万円=400万円(相続税評価額)
となり、1,600万円の評価減となります。
相続税の税率が仮に20%だった場合、320万円の相続税が減額されたことになります。
非常に大きな減額ですね。
このように「小規模宅地の特例」は要件さえ満たせば非常に有効な節税になるわけです。
《小規模宅地の特例(貸付事業用)》
そこで今回はタイトルにもあるように、上記の3種類の特例のうち、「貸付事業用の小規模宅地」について解説したいと思います。
「貸付事業用の小規模宅地」は「居住用の小規模宅地」と同じく適用頻度の多いものです。
ではどう言った方が利用されるのかというと、
〇マンション・アパート等の不動産経営をされている方
〇月極駐車場などを経営されている方
などです。
相続財産に占める不動産の割合は、現金預貯金に次いで第2位となっていますので、該当する方も多いと思われます。
《小規模宅地の特例(貸付事業用)》の要件
では「貸付事業用小規模宅地の特例」の要件どういったものでしょうか。
以下に列記してみました。
〇被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族が事業を行っていた
〇相続又は遺贈による取得
法定相続人には限らない。遺言により他の親族が取得した場合でも適用が可能。
〇取得者は被相続人の「親族」であること
取得者は「親族」に限定されている。
「親族」とは「6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族(民法725)」であることから被相続人の配偶者の甥姪が取得した場合でも可能ということである。
〇原則、相続税の申告期限までに取得者が引き継ぎ事業を継続していること
つまり相続税の申告期限までに遺産分割協議が完了していることが原則である。
ただし、「申告期限後3年以内の分割見込み書」を提出することにより、申告期限後3年以内であれば、更正の請求によって適用可能である。
〇その宅地を相続税の申告期限まで保有していること
〇建物又は構築物の敷地であること
駐車場の場合、アスファルト舗装や砂利敷きがない青空駐車場の場合は、建物又は構築物の敷地になっていないため特例適用は認められない。(砂利敷の場合は砂利の量など構築物と認められる場合に限られる)
〇その他
不動産貸付が事業的規模になっていない場合でも、評価減の特例は認められる。
事業的規模に至らない不動産の貸し付けは「事業に準ずるもの」として特例の適用を認めている。
ただし、この場合には「相当な対価を得て継続的に」とする条件を必要とする。つまり資金収支が黒字でなければならないということである。
「貸付事業用の小規模宅地」の場合、事業的規模かどうかによって、限度面積及び減額割合に変動はなく限度面積200㎡ 減額割合50%である。
まとめ
「小規模宅地の特例」は減額幅も大きく、税制改正も頻繁に行われる項目です。
特例を正確に理解しておけば、相続開始前に対応することで大きな減額になるかもしれません。
節税の基本は現在の状況を把握することから始まります。
現在の状況を把握 ⇒ 現在の相続税額を把握 ⇒ 節税対策を考える
相続が開始されてからでは節税対策はできません。
時間を味方につけ、早めに準備にとりかかることが一番重要です。
カテゴリー: コラム