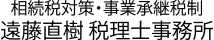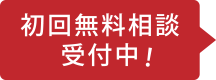遺言と相続税の関係について
コラム
2025年3月22日 土曜日
なぜ遺言書を作成するのか
遺言は遺言者の最終意思表示です。
最大のメリットは、自分の財産をできるだけ自分の意思を尊重するような形に残すことができるということです。
最近では独身の遺言者も多く、法定相続人以外に自分の財産を相続させるために遺言書を作成している方が多く見受けられます。
遺言書を発見したら
遺言書にもいくつか種類があります。代表的なものは次のとおりです。
遺言の種類
・自筆証書遺言
発見した場合、開封の前に家庭裁判所での検認が必要となります。(「自筆証書遺言保管制度」を利用したものを除く)
・公正証書遺言
自筆証書遺言とは違い、家庭裁判所での検認は必要なく開封することができます。
遺言と遺産分割について
遺言書は遺言者の最終意思を表したものですが、必ずしも遺言書通りに遺産を相続する必要はありません。
遺言書の内容を承認するのか、あるいは遺言書の内容を放棄するのかは遺言書の種類によって変わってきます。
遺言の種類
遺言には包括遺贈と特定遺贈という種類があります。
・包括遺贈
「〇〇に財産全てを遺贈する」「〇〇に財産の1/2を遺贈する」など相続分の割合を書いているものです。
・特定遺贈
「〇〇に▲▲銀行の普通預金を相続させる」のように、特定の財産について相続させる旨を記載しているものです。
遺言の放棄
特定遺贈の場合は受遺者(遺言により財産を相続するもの)と法定相続人が了承した場合に改めて分割協議を行うことができます。ただし、受遺者が法定相続人以外の場合は分割協議に参加することはできません。法定相続人以外の受遺者は特定遺贈で相続する財産以外は取得できないということです。
包括遺贈の場合は、自分が包括受遺者であることを知った日から3か月以内に家庭裁判所に放棄の手続きを行わなければいけません。
また、遺言の内容が「〇〇に財産の1/2を遺贈する」というような内容だった場合、どの財産を相続するかを法定相続人とともに遺産分割協議を行う必要があります。
相続税の計算
相続税を計算する場合は、通常、相続財産の総額から債務・葬式費用を控除し、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた後に税率を掛けて相続税額を算出します。
遺言が発見された場合もこの計算は変わりません。
法定相続人以外の方が遺言により財産を相続したとしても、相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」のままで、基礎控除額が増えるということはありません。
相続税の注意点
遺言により法定相続人以外の方が財産を相続した場合、基礎控除以外に以下のような注意点があります。
・死亡保険金の非課税
死亡保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」となっていますが、法定相続人以外の方が受け取った死亡保険金については非課税の適用はありません。
・相続税の2割加算
遺言により財産を相続した方が、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外である場合は、通常計算した相続税の額に2割加算されます。
・債務控除
特定受遺者が被相続人が負担すべき債務を代わりに負担した場合、相続税の債務控除の対象にはなりません。
遺言書が発見された場合の相続手続きは、通常の場合と違い大変複雑になってきます。
受遺者が法定相続人を把握することが困難な場合や、法定相続人との付き合いが希薄な場合なども多くあるため早めの申告準備が必要となってきますのでご注意ください。
カテゴリー: コラム