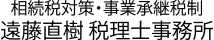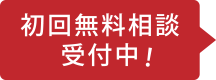相続開始直前の節税が可能に!
コラム
2025年1月11日 土曜日
令和5年度の税制改正の結果、「相続時精算課税制度」が使いやすくなりました。
昨年12月に令和7年度の税制改正大綱が発表されましたが、改めて過去に改正があった「相続時精算課税制度」について整理してみたいと思います。
【税制改正の内容】
令和5年度の税制改正において、相続税・贈与税について資産移転の時期の選択に対する中立性を高める観点から、相続時精算課税制度の使い勝手向上を図るため、暦年課税と同様、基礎控除を創設する措置が講じられました。
まとめると
・贈与税の暦年課税と同様に相続時精算課税にも基礎控除110万円が創設された。
・贈与の金額が110万円以下の場合は、最初の年に相続時精算課税選択届出書の提出のみで可能であり、かつ、翌年以降の贈与の金額が110万円以下の場合は申告も届け出も不要となった。
・相続時精算課税に係る特定贈与者に贈与が発生した場合は、相続時精算課税に係る基礎控除後の残額を相続税の課税価格に加算する。
という内容である。
【旧制度との比較】
従来の「相続時精算課税制度」は暦年課税のような基礎控除はなく、特定贈与者から贈与により取得した財産を全て申告する必要があり、また、特定贈与者に相続が発生した場合は「相続時精算課税制度」を適用したすべての財産を贈与時の価額で相続財産に計上しなければなりませんでした。
なので、相続対策に生前贈与を利用しようと考える方にとっては「どうせ贈与をしても結局相続財産に加算されるのだから制度を使っても意味がない」として相続対策には不向きとされていました。(将来値上がりが期待されるものであれば、相続時に加算される価額は贈与時の価額なので節税効果がみられる場合もあります。)
今回の改正で贈与の都度申告する必要もなく、また、相続時に加算される金額も基礎控除後の金額になるため使い勝手が良くなったうえにある程度の節税効果も見られるようになります。
ちなみに、同年の税制改正において、令和6年1月1日以後の贈与について暦年課税を適用する場合の相続に引き戻される期間が、相続開始前3年から7年になりました。
生前贈与を相続税の節税対策に利用される人は数多くいます。
そして多くの人が暦年課税の基礎控除である110万円以下の贈与を毎年繰り返しています。
これらの方々は今までの暦年課税から相続時精算課税へ切り替える一択です。
暦年課税では相続前7年間の贈与が無駄になってしまうからです。
【改正後の暦年課税と相続時精算課税の比較】
(暦年課税)
基礎控除・・・110万円
申告義務・・・110万円を超えて場合
相続時加算・・・死亡前7年間に被相続人から贈与を受けた財産価額(3年超7年以内の財産については100万円を控除できる。)
(相続時精算課税)
基礎控除・・・110万円
申告義務・・・110万円を超えた場合(ただし初年度は「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要
相続時加算・・・制度を利用した全期間において、基礎控除の110万円を超えた残額
【贈与者が贈与をした年に死亡した場合】
今回の税制改正で最も重要なポイントはここではないでしょうか。
取り扱い自体は何も変わっていませんが制度をよく理解していると相続開始直前においても節税対策が可能となるケースが存在します。
相続開始時期が近づいてくると何か節税できることはないか考えることはごく自然なことです。
こういった場合に抵触することが「贈与者が贈与をした年に死亡した場合」の取り扱いです。
では「贈与者が贈与をした年に死亡した場合」の取り扱いはいったいどうなっているのか一度整理したいと思います。
(暦年課税)
《受贈者が相続・遺贈により財産を取得した場合》
一番多いケースですが、この場合は相続開始年に贈与により取得した財産は相続税の申告に計上するため贈与税の申告は必要ありません。
つまり節税にはならないということです。
《受贈者が相続・遺贈により財産を取得しなかった場合》
このケースは相続・遺贈により財産を取得していないため相続財産に計上する必要はありません。(相続・遺贈により財産を取得していないため相続税の申告義務そのものがないということです。)
ただし、通常の贈与税の申告の必要があります。
(相続時精算課税)
・すでに相続時精算課税制度の適用を受けている方
相続税の課税対象となるため贈与税の申告は不要です。
※令和6年1月1日以後の贈与については贈与財産の価額から110万円の基礎控除を控除した残額を加算することになります。
・初めて相続時精算課税の適用を受ける方
贈与税の申告書を提出する必要はありませんが、「相続時精算課税選択届出書」を贈与者の住所地を管轄する税務署に下記のいずれか早い日までに提出する必要があります。
〇贈与を受けた年の翌年3月15日
〇贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限
【重要ポイント】
従来の制度であれば相続開始の直前に、相続対策として、被相続人の財産を生前に贈与したとしても暦年課税の場合は3年(現在は7年)、相続時精算課税の場合は全ての適用期間について相続加算の対象になり節税対策にはなりませんでした。
しかし今回の改正により、「相続時精算課税制度」の適用を受ける方(相続開始後に受けようとする方も含む。)については、相続加算される期間は変わりませんが加算される金額が相続時精算課税の基礎控除後の金額になるため、相続開始直前の対策が可能となります。
その場合、相続税の課税価格は相続人一人につき最高110万円しか減少しませんが、相続人が3人いれば330万円、年をまたぐことができれば2年合計660万円減少します。仮に相続税の税率が15%であったとすれば99万円の節税ができることになります。
【まとめ】
税制改正により相続時の贈与加算が3年から7年になったことばかりを取り上げがちですが、正しく法律を理解することでいろいろな可能性が出てきます。
相続対策はいかに生前に計画を立てているかにかかっています。
ぜひ一度、早めのご相談をお願いします。
なお、上記の直前の対策は贈与契約を前提としているため、贈与者に意思能力があることが必須条件です。
また参考事項として、生前に葬式等の準備のために預金を動かした場合の取り扱いを示しています。
参考:
相続税の申告書を作成していますと、相続開始直前に被相続人の口座から預金を出金しているのが散見されます。
これは脱税をしようと思っているわけではなく、相続開始後にすぐに訪れるであろう葬式費用等の準備のために行われることがほとんどです。
そいていざ申告書を作成する際には、相続開始直前に出金した金額から葬式費用等に費消した金額の残額を相続財産に計上するものとして勘違いしています。
正しくは、相続開始の時点で実際に残っていた現金を相続財産に計上し、費消した葬式費用を相続税の債務・葬式費用として計上するのです。
カテゴリー: コラム