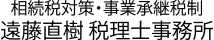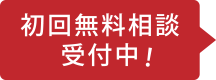相続人名義の預金と相続財産の関係について
コラム
2024年12月14日 土曜日
当事務所が開業して6年目を迎えております。
相続税や贈与税について、お客様の関心は高く予想以上に多くの問い合わせをいただいております。
その中でダントツに質問が多い事項が「家族名義預金」についてです。
平成27年に相続税の基礎控除が現在の金額(3,000万+600万×法定相続人の数)に改正されてから、相続税の申告が身近なものとなってしまいました。
自分にもしものことがあったとき、残された家族に少しでも多くの資産を残したいと思い節税について少しずつ考え始めます。
しかし、節税と言っても実際は「家族名義預金」を作成している場合が多く散見されます。
「家族名義預金」を作るということは様々なリスクがあります。
《家族名義預金のリスク》
1 税務調査の対象になりやすい
2 税務調査で指摘された場合、重加算税が賦課される場合が多い
3 「家族名義預金」であるがゆえに、相続開始後に自由に運用することが難しい
4 本来適切な相続対策に使う時間が奪われてしまう
など、たくさんのリスクがあります。
《不動産や有価証券の名義人について》
不動産や株式等の有価証券を贈与により取得した場合には、原則として、その時にその名義人に対して贈与があったものとして取り扱うこととなっています。(相続税法基本通達9-9)
したがって不動産や株式等の有価証券等のように、その登記・登録した名義人がその所有者として第三者に対する対抗要件を取得することになるような場合については、その真実の権利者がその名義人以外の者であることについて積極的な反証がない限り、課税実務上はその当該不動産の登記名義人又は当該有価証券の登録名義人が真実の所有者であると取り扱われています。
《預貯金の名義人の取り扱いについて》
上記の取り扱いは、あくまで不動産や有価証券の名義人が第三者に対して対抗要件を取得する場合に限った取り扱いです。
不動産や有価証券と性質の異なる預貯金などの金融資産には、上記のような取り扱いはありません。
預貯金等の金融資産は、法的には、その金融資産の名義人が常に真の権利者であると推定することができない性質のものであり、名義人以外に真実の権利者が存在することが多々あるからです。
【実質の権利者の判定要素】
では、いったい事柄が実質の権利者の判定要素となるのか下記に列記してみました。
1 その預貯金を実際に拠出したのは誰か
2 その預貯金の口座開設を行ったのは誰か
3 その預貯金の入出金を行っているのは誰か
4 その預貯金が引き出された場合の使途は何か
5 その預貯金通帳の保管はどこで誰が管理していたのか
6 その預貯金に使用されている印鑑はどこで誰が管理しているのか
7 その印鑑はほかの名義人の預貯金の引き出しに使用されていないか
8 その預貯金の届け出の住所は名義人の住所になっているか
9 その預貯金の金融機関を名義人が扱うことに不自然な点はないか
など、実際の税務調査では上記なような要素を基にその預貯金が被相続人のものか真実の名義人の物かを判断していきます。
たまに「贈与税の申告をしているので実際に贈与が行われていた証拠になる」という方もいらっしゃいますが、贈与税の申告が行われているからと言って実際に贈与が行われていたと推定はできません。
仮に被相続人が管理していた金庫の中から贈与税の申告をしている孫名義の預貯金通帳が発見された場合は、相続財産に計上する必要があります。そして故意に申告から除外していたとみなされ重加算税が賦課される可能性が非常に高くなります。
また、「家族名義を作ったのは10年以上前だからもう時効でしょ。」といわれる場合もありますが、「家族名義預金」であると認定された場合は、そもそもその預貯金が被相続人財産であるため時効の対象にはなりません。
上記の中でも申し上げた通り、家族名義預金を作成すると真に必要な節税対策の時間が無駄に奪われます。
相続税の計算に含まれる生前贈与の期間が相続開始前3年から7年に伸びました。
と同時に今まで使いづらかった「相続時精算課税」の制度に基礎控除が創設され、手続きも簡易になっています。
またNISA制度も使いやすくなっていることから、新たな資産防衛の対策も広がっています。
節税対策のキモは
1 とにかく現状の財産の正確な把握
2 節税対策について親族で一度相談する
です。
事前に財産を把握し、相続人全員で意見を出し合うことで節税対策も行え、かつ、無駄な相続争いも少なくなります。
年末・年始は親族が集まる機会も多いと思いますので一度検討してみてはいかがでしょうか。
カテゴリー: コラム